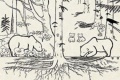パナマ運河の拡張工事が進んでいる。2016年に完了すれば、これまで米国の西海岸に寄港するしかなかった大型船舶が、積荷を直接メキシコ湾や東海岸の港まで運べるようになる。ところが、こうした船舶は同時に、意図せず大量の外来生物を運んでしまう。その脅威や規模について、米国の研究者がこのほど学術誌『Diversity and Distributions(多様性と分布)』に発表した。
パナマ運河には新たに第3の閘門(こうもん)が設置されるほか、水路も広く、深くなる予定だ。航行可能な船舶の大きさは、現在よりも長さ71メートル、幅16メートル拡大し、最大で全長366メートル、全幅49メートルの船舶が通れるようになる。
メキシコ湾および東海岸沿いの港町では、すでに現在のパナマックス(パナマ運河を通過できる船の最大の大きさ)を超える「ポスト・パナマックス」の巨大船舶のために、港の浚渫(しゅんせつ)、倉庫エリアの拡大、大型クレーンの設置などの準備が進められている。
米スミソニアン環境研究センターの研究者ジム・ミュアヘッドらは今回の研究で、パナマ運河の拡張後、東海岸やメキシコ湾岸に外来生物が侵入する可能性がどれほど高まるかを推定した。
それによると、現在西海岸を利用している船舶のうち、約25%がパナマ運河を通過し、メキシコ湾や東海岸を目指すようになるという。いくつかの港では、寄港する船舶の数が3倍に増え、それぞれの船も大きくなる見込みだ。
その際、外来生物が移動するパターンはふた通り。ひとつはバラスト水に生物が含まれている場合。もうひとつは、船体の水に浸かった部分(浸水面積)に生物が付着している場合だ。ミュアヘッドらは、船のバラスト水の量と浸水面積が各港においてどう変化するかを調べた。その結果、標準的な東海岸の港で排出されるバラスト水の量は、最初の5年間で従来の2倍になり、メキシコ湾沿いでは78%増加することがわかった。浸水面積は、どちらの地域でも3倍近くになることもわかった。
ゼブラ貝の恐怖ふたたび?
船で別の港へ運ばれた外来生物は、大半が死滅し、人知れず消えていく。しかし生き延びることに成功したものは、在来種を駆逐する危険をはらんでいる。たとえば1980年代末に五大湖に侵入したゼブラ貝は、周辺の生態系を大きく乱し、送水管などを詰まらせて数十億ドルに及ぶ被害をもたらした。
数十年間にわたり、太平洋を横断する巨大船舶を迎え入れてきたカリフォルニア州には、海の外来生物が米国の他の地域よりも多く生息する。そして東海岸とメキシコ湾岸にもすでに、パナマ運河を経由して入り込んだとみられる外来種が散見される。バラスト水と一緒にやってきたと思われるイソガニは、いまや東海岸全域で見つかる。
パナマ運河の拡張後、侵入してくる外来生物の種類や規模は、港によって異なると考えられる。その一因となるのが、各港で行われる取引の種類の違いだ。たとえばメキシコ湾沿いの港には、石油製品を積んだ超大型タンカーがやってくる。タンカーは常に液体貨物あるいはバラスト水を満載しているため、一度に大量のバラスト水を排出する傾向にある。
一方、多様な一般消費財を運ぶコンテナ船は、主に東海岸の港へ向かう。こうした船舶の場合、ひとつの港で排出するバラスト水の量はそう多くない。コンテナ船はいくつもの港に寄港して荷を降ろし、代わりに別のコンテナを積んでいく。寄港する港が増えれば増えるほど、新たな外来生物の移動に寄与する可能性も増加する。
動植物の均一化への懸念
この研究に関わった学者たちは、今こそ行動を起こすべきだと主張する。「外来生物が増えそうな場所が事前にわかっていれば、それが実際に現れる前に防御策を講じることができます」とミュアヘッドは言う。
大半の船舶に対しては、米国の水域に入る前の沖合でバラスト水を交換することがすでに義務付けられており、これによっておよそ90%の生物が排除される。将来はさらに厳しい規制が導入される予定だ。とはいえ、船体に付着した生物については、まだ効果的な対策がなされていない。
こうした問題は、パナマ運河特有のものではない。地中海と紅海を結ぶスエズ運河でも現在、大規模な拡張工事が進められている。昨年12月には、ニカラグアで新たな運河の工事が着工した。また北極の氷が解けていることから、ロシア沿岸を通る北東航路を使う船も増えている。「こうした新たな運河の開通や拡張が、世界の動植物の均一化を大幅に加速させてしまうのです」と、同研究の共同執筆者マーク・ミントンは語る。